11月に入り、秋の深まりと共に気温が下がる一方で、南の海上ではまだまだ熱帯低気圧の動きが活発です。2025年の台風シーズンは一旦落ち着きかけたものの、11月に入っても新たな“台風のたまご”が出現し、注目を集めています。
今シーズン最後の大型台風となる可能性のある「26号候補」の動向に、気象専門家や一般の関心が集まっています。
米軍合同台風警報センター(JTWC)やヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)、そしてWindyなどの最新モデルを踏まえ、現在のたまごの発生状況から日本への影響予測まで詳しく解説します。
11月4日時点の台風26号“たまご”発生状況
2025年11月4日午前3時現在、気象庁公式発表によると、新たな熱帯低気圧がカロリン諸島付近で発生しています。
この熱帯低気圧は直近24時間以内に台風に発達すると見込まれており、次に発生した台風は「26号」として命名される可能性が高まっています。
- 発生場所:カロリン諸島付近(中心気圧約1004hPa)
- 最大風速:約15m/s(中心付近)、最大瞬間風速23m/s
- 移動速度:西へゆっくり進行中
この熱帯低気圧は、11月中旬までは西進しながら海面の高い温度と湿度により発達条件が整っています。
一方で北西方向への進路も示されており、今後の太平洋高気圧の動き次第では日本列島へ接近する可能性も完全には否定できません。
米軍JTWCの最新進路予想
米軍合同台風警報センター(JTWC)は、この熱帯低気圧を既に“高い発達可能性(HIGH)”として警戒レベルを引き上げました。
予想では、11月5日頃には台風26号に昇格し、その後は北西〜北北西方向に向かうと分析しています。
- 発達速度:速度はゆっくりだが確実に台風化へ
- 進路予想:カロリン諸島からフィリピン東方を通過し、沖縄方面へ接近の可能性あり
- 強度予測:最大風速は台風の中〜強度に達する見込み
この段階で注意点は、「太平洋高気圧の張り出し具合」で進路が大きく左右される点です。
過去のケースでは、偏西風の影響で進路が急に北東に変わることもあり、九州から関東にかけて広範囲で警戒が必要となる可能性があります。
ヨーロッパECMWFモデルの解析と予測
ECMWFモデルの最新予測でも、11月5日前後にカロリン諸島で台風成形が見込まれており、その後の動きは米軍予想とほぼ一致しています。
注目は、ECMWFが示す5〜10日先の長期的な進路予想で、フィリピン東海上からゆっくりと北西に進み、その後偏西風の影響を受けて北東にカーブする可能性が高いとされています。
- 低気圧の中心気圧低下予想:1000hPa台前半から980hPa台へ
- 長期進路:フィリピン東方〜沖縄〜九州ルートの確率増大
- 強風域と降雨域が広範囲に拡大の可能性
ECMWFの特徴は、早期から複数シナリオを示すことで防災計画に役立つ点であり、数日単位での進路変動に常に注視する必要があります。
Windyの最新気象データによる台風動向
Windyの11月4日最新マップでは、カロリン諸島付近の熱帯低気圧が強風域を拡大しつつある様子が確認できます。
中心の気圧は1004hPaから徐々に低下傾向にあり、最大風速は20m/s近くに達する見込み。
上層の風の環境も比較的穏やかで、垂直方向に発達しやすい状況です。
- 強風域の広がり:半径200〜300kmに拡大中
- 海面水温:29〜30℃で台風成長に好適な条件
- 上層風:弱風域が維持されており、発達促進要因
また、日本列島の南岸には秋雨前線がすでに南西から停滞しており、この台風が接近または周辺を通過すれば影響で雨風が強まることが予想されます。
今後の日本への影響と注意点
まだ先行きが不確定とはいえ、11月に台風が日本付近に接近するのは例年稀なケースであり、警戒すべき段階です。
大きなポイントは以下の通りです。
- 台風26号は11月5日頃に正式発生の見込みで、その後数日以内に沖縄方面へ接近の可能性
- 太平洋高気圧の配置次第で進路が九州から関東にかけて変動しやすい
- 台風自体の強さは中〜強度予想で、沖縄・九州で強風・大雨のリスク増大
- 秋雨前線と合わさることで広範囲にわたる長雨・土砂災害の可能性にも注意が必要
- 交通機関の遅延・運休情報はこまめにチェックし、停電に備えた準備も推奨される
まとめ
- 11月4日現在、「台風26号」のたまごがカロリン諸島で発生し、24時間以内に台風に昇格見込み
- 米軍JTWCはすでに“高い発達可能性(HIGH)”と評価し、北西〜北北西進路を予測
- ヨーロッパECMWFモデルも同様の動きを示し、長期予測で日本接近の可能性あり
- Windyの風速・気圧データは成長フェーズを示しており、台風化は確実視される
- 日本への影響は11月中旬にかけて警戒が必要で、特に沖縄・九州・関東での大雨・強風に注意
- 防災対策は早めの備えと、最新情報の継続的確認が重要
秋の台風は進路変動が激しく短期間で変化することも多いので、最新のデータをこまめにチェックしながら、冷静で確実な備えを心掛けましょう。
※本記事の内容は執筆時点の情報をもとにご紹介しています。詳細は変更となる場合がありますので、必ず最新の情報は公式サイト等でご確認ください。
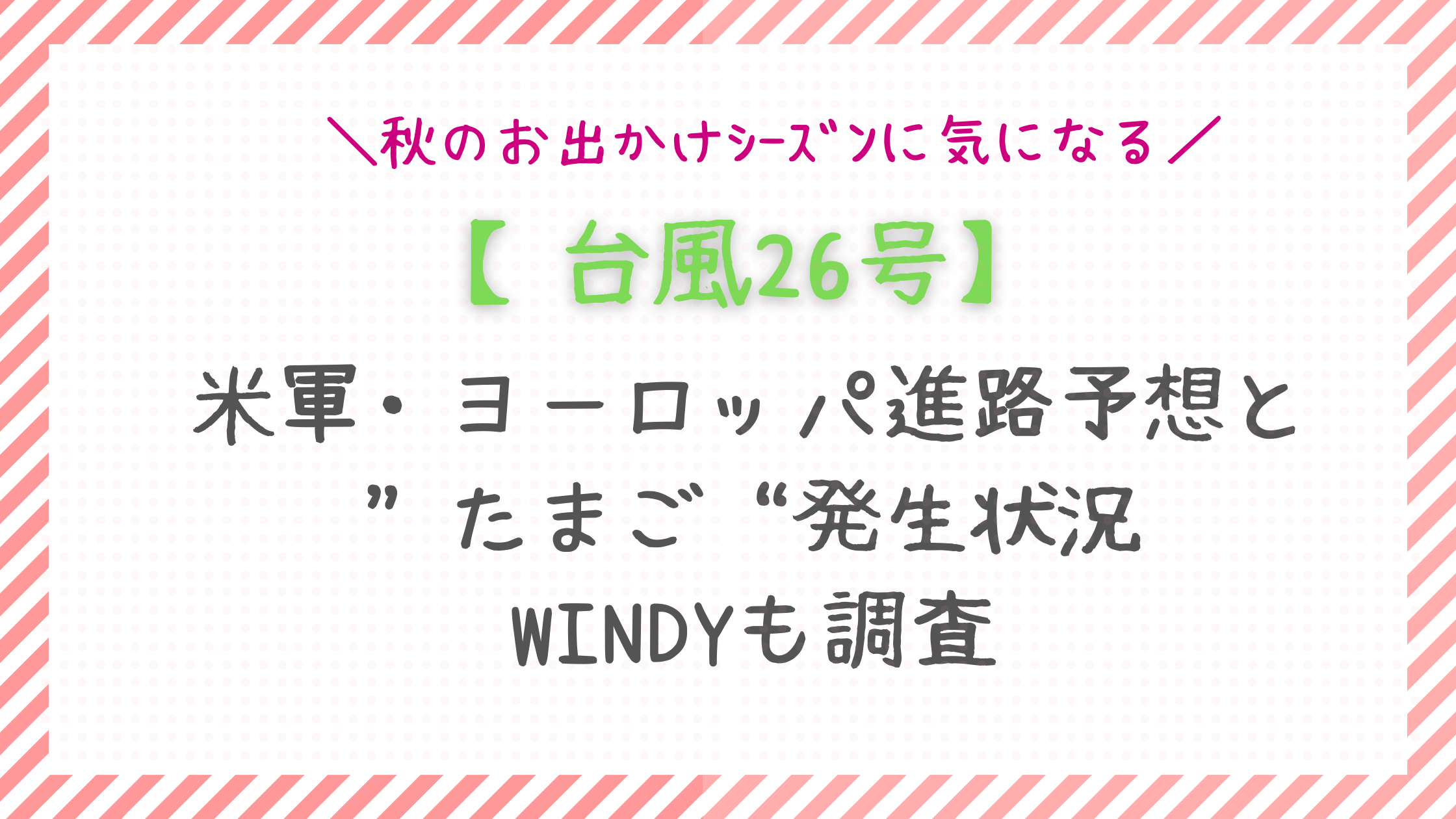
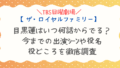
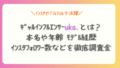
コメント